第1回EUセミナー
「岐路に立つヨーロッパ―EUのガバナンス―」
実施報告
| 実施日 | 2012年9月28日(金)~30日(日) |
|---|---|
| 会場 | 大学セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1) ※交通案内はこちら |
| 主催 | 公益財団法人大学セミナーハウス |
趣旨
一昨年以来のユーロ危機はEU統合に内包された構造的不均衡を改めて問題視する機会となった。我が国においては統合について悲観的な論調が一気に強まった ように見える。
しかし統合の試行錯誤はこれまでの統合の歴史で繰り返されてきたところである。
困難に際して、加盟国の間で常に統合を前進させようという、いわば「政治的意思」が存在するからこそ困難の克服は可能となったのである。
「グローバリゼーション」の時代においては世界が同じ問題を共有し、克服していくプロセスが様々な形で拡大していく。それぞれの地域によってそのあり方は違っていても。大きな流れとし同じ地域の諸国の間での協力は不可欠である。
本 セミナーは以上のような関心から、特に若い人々が日本の内外情勢を考えていく上での思考の一里塚として、EU統合をより広く理解していくことを意図して、 今年から始まるプログラムである。第一回目にあたる今年のセミナーは、「EUガバナンス」をテーマに経済・通貨、政治統合、EU法、環境問題、EUの対外 関係などの個別のセッションを設けて、個別の議論を行うと同時に、全体会議でEUのガバナンスとは何かを考えてみる。EUに本代表部大使にも講演いただ く。学生諸君の多数の参加を望んでいる。
しかし統合の試行錯誤はこれまでの統合の歴史で繰り返されてきたところである。
困難に際して、加盟国の間で常に統合を前進させようという、いわば「政治的意思」が存在するからこそ困難の克服は可能となったのである。
「グローバリゼーション」の時代においては世界が同じ問題を共有し、克服していくプロセスが様々な形で拡大していく。それぞれの地域によってそのあり方は違っていても。大きな流れとし同じ地域の諸国の間での協力は不可欠である。
本 セミナーは以上のような関心から、特に若い人々が日本の内外情勢を考えていく上での思考の一里塚として、EU統合をより広く理解していくことを意図して、 今年から始まるプログラムである。第一回目にあたる今年のセミナーは、「EUガバナンス」をテーマに経済・通貨、政治統合、EU法、環境問題、EUの対外 関係などの個別のセッションを設けて、個別の議論を行うと同時に、全体会議でEUのガバナンスとは何かを考えてみる。EUに本代表部大使にも講演いただ く。学生諸君の多数の参加を望んでいる。
(EUセミナー企画委員長/渡邊 啓貴)
実施報告
開会の冒頭に、EUセミナー企画委員長の渡邊啓貴先生よりセミナーの開催主旨を説明し、続いて六つの分科会講師の先生方より提題の説明をした。その後、分 科会の時間になり、六つの分科会のテーマ、第1分科会「ユーロ危機と通貨統合」、第2分科会「エネルギーと環境」、第3分科会「EUのアイデンティ ティ」、第4分科会「グローバルプレイヤーとしてのEU」、第5分科会「EU統合のガバナンスと政策過程」、第6分科会「拡大EUの対外戦略」をめぐり、 徹底的にEUの加盟国、多国間の政治、経済について分析することによって、EUのガバナンスの全体像の究明に至るよう熱論を展開した。その結果を、中間報 告、最終報告の二回で六つの分科会での議論の結果を全体会において発表し、信頼できる情報をみんなで共有することができたようだ。
開会中、EU駐 日代表部副代表を迎え、「EUのガバナンス」をテーマにした特別講演を開催した。コリンズ氏の講演を聞き、参加者のEUに対する認識を深めた。講演後の質 疑応答時間において、学生が直接英語で講演者に質問し、会場は情報交換の交流の場になった模様が記憶に残る。
本セミナーの中心問題のEUガバナン スについて専門ではないので、ここではまとめる資格がないが、このセミナーでEU地域を研究する大学院生、EU地域について勉強する学部生、それぞれ自分 なりのEUに関する知識を吸収することができ、各自の今後の研究や勉強に大変役立ったと考える。
開会中、EU駐 日代表部副代表を迎え、「EUのガバナンス」をテーマにした特別講演を開催した。コリンズ氏の講演を聞き、参加者のEUに対する認識を深めた。講演後の質 疑応答時間において、学生が直接英語で講演者に質問し、会場は情報交換の交流の場になった模様が記憶に残る。
本セミナーの中心問題のEUガバナン スについて専門ではないので、ここではまとめる資格がないが、このセミナーでEU地域を研究する大学院生、EU地域について勉強する学部生、それぞれ自分 なりのEUに関する知識を吸収することができ、各自の今後の研究や勉強に大変役立ったと考える。
全体会(パネルディスカッション)

前左から渡邊啓貴先生、田中素香先生、蓮見雄先生、中西優美子先生、
押村高先生、福田耕治先生、小久保康之先生
特別講演
テーマ:「An Introduction to the European Union and EU-Japan Relations」

講演者:MAEVE COLLINS(マエヴ・コリンズ)駐日欧州連合代表部公使・副代表
各分科会講師の提題スピーチ
第1分科会 講師 田中 素香 先生

EU通貨統合によって史上初めて単一の共通通貨が流通することとなった。それから10年余り、ユーロは2010年から翌年にかけて危機に陥った。米英を震 源地とする世界金融危機に対して、ユーロ圏諸国の対応力の格差が劇的な形で明らかとなった。ギリシャなど新興諸国と西欧・北欧の先進諸国との危機対応力の 格差が、南欧諸国の財政危機・政府債務危機(ソブリン危機)の形で顕在化し、ソブリン危機は金融・銀行危機に発展して、ユーロ圏のみでなく世界経済にも悪 影響を及ぼした。
第1分科会では、このユーロ危機について、広い視野から総合的に分析し、EU・ユーロの対応の発展、将来展望について考える。全体として、EU経済統合の最前線にある通過統合の試練を通じて、21世紀前半にEU統合がどのような発展を遂げるのかを、一緒に考えたい。
第1分科会では、このユーロ危機について、広い視野から総合的に分析し、EU・ユーロの対応の発展、将来展望について考える。全体として、EU経済統合の最前線にある通過統合の試練を通じて、21世紀前半にEU統合がどのような発展を遂げるのかを、一緒に考えたい。
第2分科会 蓮見 雄 先生 中西 優美子 先生


EUは、エネルギーの確保と持続可能な経済発展の同時達成という課題に挑戦している。この分科会では、EUのエネルギー・環境問題を経済的及び法的観点か ら取り扱う。排出枠取引制度など、エネルギー・環境問題に経済的手法を取り入れた法的措置も見られるようになってきている。エネルギーと環境の問題を同時 に、しかも経済と法という両方の観点から問題を眺めることで、より具体的な対策を立てることが可能になる。エネルギーについては、石油・天然ガスなど化石 燃料の確保と利用効率の改善、再生可能エネルギーの導入とその前提となるエネルギーネットワークの整備、原子力エネルギーの安全性、共通エネルギー政策の 可能性などが議論されることになる。環境については、地球温暖化政策への取り組みが議論の対象となる。
第3分科会 講師 押村 高 先生

EUの建設は、制度や機構の面では軌道に乗ってきましたが、一方で各種意識調査を見る限り、ヨーロッパ人がEUに対して抱くイメージは余り改善されていま せん。民主的コントロールが不十分であることへの不信、決定権限が各国の民主的政府からEU機構へシフトしまうことへの不満にも、根強いものがあります。 本セクションでは、ヨーロッパが企業、資本、官僚による「エリートのEU」から「民衆のEU」に変るためには何が必要なのかの分析から始め、地域ガバナン スの安定には構成国を横断する集団アイデンティティの醸成が重要であることを再確認し、さらにEUがこれまで取り組んできた教育、文化、メディアの分野に おける政策を評価して、「意識のヨーロッパ化」における課題とは何かについて検討します。
第4分科会 講師 渡邊 啓貴 先生

ギリシアをはじめとする南・西欧諸国の財政危機をめぐってユーロの行く末が懸念されている。ドル・円と並ぶユーロ通貨圏の危機がグローバルな影響をもつことは明らかである。
本 分科会では、EUの存在をグローバルにとらえつつ、経済圏としてだけではなく、政治・外交・安全保障面も含めてその対外関係について考えていきたい。同時 に、そのことはEUそのものがハードパワーとしてだけでなく、価値規範を共有し、伝達することを通して影響力を持つ存在であることを意味している。こうし た観点から、EUの国際社会(国際機関・アメリカ・アジア)との関係について考えていくことが本分科会の目的である。
本 分科会では、EUの存在をグローバルにとらえつつ、経済圏としてだけではなく、政治・外交・安全保障面も含めてその対外関係について考えていきたい。同時 に、そのことはEUそのものがハードパワーとしてだけでなく、価値規範を共有し、伝達することを通して影響力を持つ存在であることを意味している。こうし た観点から、EUの国際社会(国際機関・アメリカ・アジア)との関係について考えていくことが本分科会の目的である。
第5分科会 講師 福田 耕治 先生

EU機構と政策過程に焦点を当て、欧州ガバナンスの機能と構造を取りあげる。欧州の民主的ガバナンスの仕組みと正統性の問題、EUの金融・通貨、環境・エネルギー、社会・労働、文化、対外政策等の意思決定について討論を通じて理解を深めたい。
EU 諸機関の機構をめぐる諸問題および加盟国の統治機構との間の権限関係、各公共政策過程と欧州市民との関係を考える。EU諸政策における多様なガバナンス方 式の比較を通じて、リスボン条約の意義と問題点を理論的かつ実証的に検討を行い、欧州統合の全体像を俯瞰し、EUを体系的に捉えられるようにしたい。
EU 諸機関の機構をめぐる諸問題および加盟国の統治機構との間の権限関係、各公共政策過程と欧州市民との関係を考える。EU諸政策における多様なガバナンス方 式の比較を通じて、リスボン条約の意義と問題点を理論的かつ実証的に検討を行い、欧州統合の全体像を俯瞰し、EUを体系的に捉えられるようにしたい。
第6分科会 講師 小久保 康之 先生
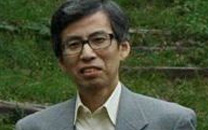
2004年および2007年の拡大によりEU加盟国は27カ国となった。今後も西バルカン諸国が順次加盟してゆく予定であるが、同時にトルコの加盟問題と いう大きな課題をEUは背負っている。さらに、拡大EUの近隣地域を政治的・経済的に安定させることが拡大EUにとっての急務となっている。それ故、更な る「拡大」および近隣政策(ENP)は、拡大EUにとって極めて重要な対外戦略と言えよう。本分科会では、そうした拡大EUの対外戦略についての理解を深 めることに重点をおきつつ、ロシア、中国、日本、アジアといった他の地域・諸国との関係にも気配りをしながら、拡大EUの対外戦略全般について参加者と討 論してゆく。
分科会討論の模様

第1分科会
「ユーロ危機と通貨統合」

第2分科会
「エネルギーと環境」

第3分科会
「EUのアイデンティティ」

第4分科会
「グローバルプレイヤーとしてのEU」

第5分科会
「EU統合のガバナンスと政策過程」

第6分科会
「拡大EUの対外戦略」
全体会(分科会討論の結果報告)模様

参加者より
EU公使マエヴ・コリンズ氏講演について
東京外国語大学・教授/鶴田知佳子先生(コリンズ氏の逐次通訳担当)のゼミ生より
【青柳 詩史さん】
本日は貴重な勉強の機会をいただきまして、ありがとうございました。
講演の場で鶴田先生の通訳を拝聴するのは初めてで、きれいに整理された分かりやすい日本語訳に聞き入ってしまいました。
ま た、今回 鶴田先生の通訳を聞かせていただいたことで、普段の自分の通訳の改善すべき点を振り返ったり、英語力や通訳の訓練を行うとともに、より一般常識や専門知識 を身につけていきたいとあらためて感じたり、いろいろなことを考えるよい機会となりました。講演の内容もとても興味深かったです。
【高山 千晶さん】
講演会では、鶴田先生の逐次通訳をお聞きすることができ、大変貴重な機会となりました。特に、先生がオーディエンスに伝わりやすいよう情報の順番を工夫して訳されていたところが勉強になりました。
また、逐次通訳はその場の雰囲気にもかなり影響すると先生がおっしゃっていたように、公使とオーディエンスのやりとりにも先生が柔軟に対応されていたのが素晴らしいと感じました。
公 使の英語を聞いた瞬間に会場に笑いが起きるなど、聞き手の多くが英語を理解しているように感じられる場面もありました。笑いが起きた後に逐次通訳するのも 大変に苦労されるだろうと感じましたが、先生が間髪入れずに通訳を始め、スムーズな流れを終始保っていらっしゃったのが印象的でした。
先生の通訳を拝聴すると同時に、逐次通訳の実際の様子を知る大変貴重な機会でした。お誘いいただき感謝しております。今後もこのような機会がありましたら、ぜひ参加したいです。
【宇多田 怜子さん】
逐 次通訳を聞くのは久しぶりでしたが、私もメモを取りながら臨みました。今回はEU公使の講演会ということで、公使のお話の中にはEUに関する固有名詞、機 関名、政策名、地名、人名などが数多く使われていました。このような固有名詞等を正確に訳出することは通訳者にとって当然のことではありますが、固有名詞 を正確に訳出することにより、通訳を聞いているオーディエンスにとっては、通訳された内容が正確であると信頼できる理由のひとつになるとも思いました。同 様にヨーロッパの歴史的背景などについても把握しておくことで、スピーチの内容をより正しく理解し、オーディエンスに正確に伝えることが可能になると思い ました。これまでも通訳を学び準備の重要さを痛感してきましたが、今回鶴田先生の通訳を聞き、しっかりと準備することは、オーディエンスに与える印象にも 大きく影響するのだと改めて思いました。
鶴田先生の通訳では、長い英語表現を日本語一言で言い換えたり、専門的なカタカナ用語に説明を加えたり、 オーディエンスに優しい配慮がなされていました。内容を正しく伝えるということは、聞く人が理解しやすいように伝えるということです。今回学んだことを参 考にして、私もこれからの通訳に活かしていきたいと思います。
また、スピーカーのEU公使と通訳者の鶴田先生の間では、互いにコミュニケーション を取りながら、スピーチの一区切りが長すぎないか、どのタイミングで通訳者にバトンタッチしたらよいかなどを確認していらっしゃいました。昨年逐次通訳の クラスで演習を行った際には切り替えるタイミングをほとんどスピーカーに任せていましたが、スピーカーと通訳者と二人で講演会を作り上げていくという意識 を持つことが重要であることを再確認しました。
最後に、講演会の内容についてですが、前回学内で開催されたEU大使の講演会と比較して、公使がよ りオーディエンスと近い距離でお話しされており、日本との関係や直近のユーロ危機などにも触れてくださったので、非常に興味深く伺うことができました。参 加者との質疑応答を通し、EUで働く方が個人として実際にどのような意見をお持ちなのかを知る良い機会でもありました。
【加藤 実佳さん】
9 月29日に大学セミナーハウスで行われた講演会は非常に勉強になりました。英語を理解できる方が多く、その分野の専門家たちの集まる中での通訳はプレッ シャーがさぞかし大きいだろうと思いました。それにも関わらず、先生の間髪入れず通訳に移る姿には驚かされました。授業で、先生は時間に限りのある講演の 流れを断ち切らないためにすぐに訳出することを心がけていたとおっしゃっていたので、通訳者には高度な通訳技術に加えて、スピーチや講演全体にわたる気遣 いが求められるのだと分かりました。通訳は言語処理能力だけではなく、多角的な視点を持ちながらさまざまな配慮が必要な仕事だと感じました。
講演 中、私も久しぶりにメモ取りをやってみました。しかし、話の区切りが長い上、通訳者のリテンション力も必要となるので、やはり逐次通訳は非常に負担が大き いと思いました。先生の頭の中はどうなっているのか・・・と思いながら先生の通訳を聞きつつ、自分のメモを見返していました。そんな私のメモ取りの集中力 は45分くらいしか続かなかったので、90分の講演を一人で担当する通訳者のすごさを改めて感じる講演会でした。
【青柳 詩史さん】
本日は貴重な勉強の機会をいただきまして、ありがとうございました。
講演の場で鶴田先生の通訳を拝聴するのは初めてで、きれいに整理された分かりやすい日本語訳に聞き入ってしまいました。
ま た、今回 鶴田先生の通訳を聞かせていただいたことで、普段の自分の通訳の改善すべき点を振り返ったり、英語力や通訳の訓練を行うとともに、より一般常識や専門知識 を身につけていきたいとあらためて感じたり、いろいろなことを考えるよい機会となりました。講演の内容もとても興味深かったです。
【高山 千晶さん】
講演会では、鶴田先生の逐次通訳をお聞きすることができ、大変貴重な機会となりました。特に、先生がオーディエンスに伝わりやすいよう情報の順番を工夫して訳されていたところが勉強になりました。
また、逐次通訳はその場の雰囲気にもかなり影響すると先生がおっしゃっていたように、公使とオーディエンスのやりとりにも先生が柔軟に対応されていたのが素晴らしいと感じました。
公 使の英語を聞いた瞬間に会場に笑いが起きるなど、聞き手の多くが英語を理解しているように感じられる場面もありました。笑いが起きた後に逐次通訳するのも 大変に苦労されるだろうと感じましたが、先生が間髪入れずに通訳を始め、スムーズな流れを終始保っていらっしゃったのが印象的でした。
先生の通訳を拝聴すると同時に、逐次通訳の実際の様子を知る大変貴重な機会でした。お誘いいただき感謝しております。今後もこのような機会がありましたら、ぜひ参加したいです。
【宇多田 怜子さん】
逐 次通訳を聞くのは久しぶりでしたが、私もメモを取りながら臨みました。今回はEU公使の講演会ということで、公使のお話の中にはEUに関する固有名詞、機 関名、政策名、地名、人名などが数多く使われていました。このような固有名詞等を正確に訳出することは通訳者にとって当然のことではありますが、固有名詞 を正確に訳出することにより、通訳を聞いているオーディエンスにとっては、通訳された内容が正確であると信頼できる理由のひとつになるとも思いました。同 様にヨーロッパの歴史的背景などについても把握しておくことで、スピーチの内容をより正しく理解し、オーディエンスに正確に伝えることが可能になると思い ました。これまでも通訳を学び準備の重要さを痛感してきましたが、今回鶴田先生の通訳を聞き、しっかりと準備することは、オーディエンスに与える印象にも 大きく影響するのだと改めて思いました。
鶴田先生の通訳では、長い英語表現を日本語一言で言い換えたり、専門的なカタカナ用語に説明を加えたり、 オーディエンスに優しい配慮がなされていました。内容を正しく伝えるということは、聞く人が理解しやすいように伝えるということです。今回学んだことを参 考にして、私もこれからの通訳に活かしていきたいと思います。
また、スピーカーのEU公使と通訳者の鶴田先生の間では、互いにコミュニケーション を取りながら、スピーチの一区切りが長すぎないか、どのタイミングで通訳者にバトンタッチしたらよいかなどを確認していらっしゃいました。昨年逐次通訳の クラスで演習を行った際には切り替えるタイミングをほとんどスピーカーに任せていましたが、スピーカーと通訳者と二人で講演会を作り上げていくという意識 を持つことが重要であることを再確認しました。
最後に、講演会の内容についてですが、前回学内で開催されたEU大使の講演会と比較して、公使がよ りオーディエンスと近い距離でお話しされており、日本との関係や直近のユーロ危機などにも触れてくださったので、非常に興味深く伺うことができました。参 加者との質疑応答を通し、EUで働く方が個人として実際にどのような意見をお持ちなのかを知る良い機会でもありました。
【加藤 実佳さん】
9 月29日に大学セミナーハウスで行われた講演会は非常に勉強になりました。英語を理解できる方が多く、その分野の専門家たちの集まる中での通訳はプレッ シャーがさぞかし大きいだろうと思いました。それにも関わらず、先生の間髪入れず通訳に移る姿には驚かされました。授業で、先生は時間に限りのある講演の 流れを断ち切らないためにすぐに訳出することを心がけていたとおっしゃっていたので、通訳者には高度な通訳技術に加えて、スピーチや講演全体にわたる気遣 いが求められるのだと分かりました。通訳は言語処理能力だけではなく、多角的な視点を持ちながらさまざまな配慮が必要な仕事だと感じました。
講演 中、私も久しぶりにメモ取りをやってみました。しかし、話の区切りが長い上、通訳者のリテンション力も必要となるので、やはり逐次通訳は非常に負担が大き いと思いました。先生の頭の中はどうなっているのか・・・と思いながら先生の通訳を聞きつつ、自分のメモを見返していました。そんな私のメモ取りの集中力 は45分くらいしか続かなかったので、90分の講演を一人で担当する通訳者のすごさを改めて感じる講演会でした。
マエヴ・コリンズ氏(駐日欧州連合公使・副代表)を囲んで記念写真

ようこそ広場(2012年9月29日撮影)
大学セミナーハウスは40年近く学生セミナーを開催してきましたが、EUをテーマにするセミナーは今回初めてだ。参加者が集まるかどうか心配だったが、募 集が開始して締切まで申込の件数が百を超え、驚くほど空前の大盛況でした。来年は第2回EUセミナーを開催する予定です。より多くの方々のご応募を期待し ます。
第1回EUセミナーに参加された皆様、2泊3日大変お疲れさまでした。又のご来館をお待ちしております。
第1回EUセミナーに参加された皆様、2泊3日大変お疲れさまでした。又のご来館をお待ちしております。
(文責:孫 国鳳)
講師兼企画委員
委員長・東京外国語大学大学院 総合国際学研究院 教授/渡邊 啓貴
青山学院大学 国際政治経済学部 教授・学部長/押村 高
東洋英和女学院大学 国際社会学部 教授/小久保 康之
中央大学 経済学部教授・日本EU学会理事/田中 素香
一橋大学大学院 法学研究科 教授/中西 優美子
立正大学 経済学部 教授/蓮見 雄
早稲田大学 政治経済学術院 教授/福田 耕治
青山学院大学 国際政治経済学部 教授・学部長/押村 高
東洋英和女学院大学 国際社会学部 教授/小久保 康之
中央大学 経済学部教授・日本EU学会理事/田中 素香
一橋大学大学院 法学研究科 教授/中西 優美子
立正大学 経済学部 教授/蓮見 雄
早稲田大学 政治経済学術院 教授/福田 耕治
参加状況
<大学等別>
東京外国語大学18名、中央大学13名、立正大学12名、東洋英和女学院大学8名、早稲田大学3名、青山学院大学7名、神戸大学2名、法政大学1名、杏林大学4名、一橋大学1名、横浜国立大学1名、上智大学1名、東京学芸大学1名、社会人4名
東京外国語大学18名、中央大学13名、立正大学12名、東洋英和女学院大学8名、早稲田大学3名、青山学院大学7名、神戸大学2名、法政大学1名、杏林大学4名、一橋大学1名、横浜国立大学1名、上智大学1名、東京学芸大学1名、社会人4名
